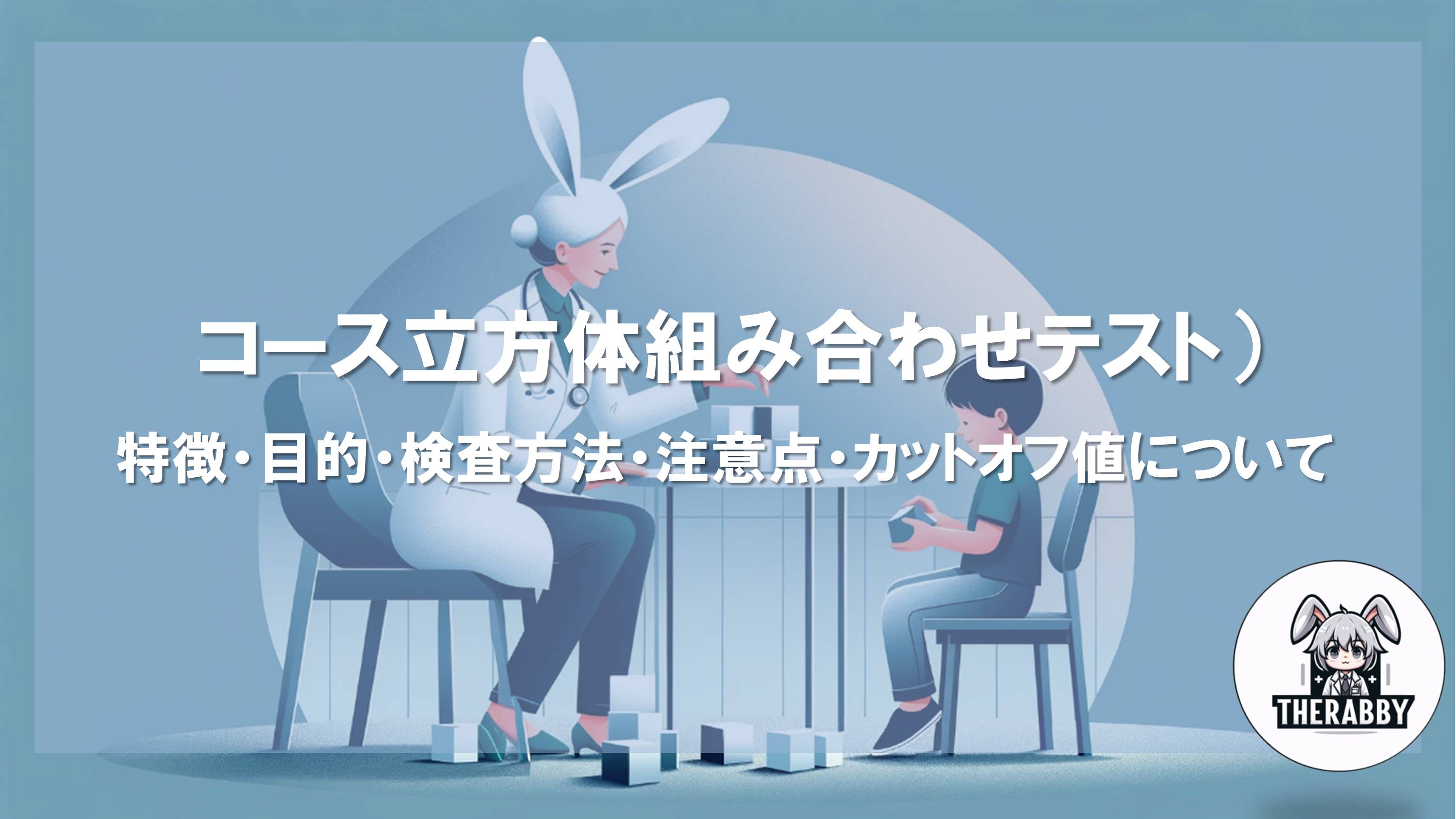被験者の知能検査の方法はいろいろありますが、“コース立方体組み合わせテスト”もその中で有名な検査の一つと言えます。
そこで今回はコースコース立方体組み合わせテストの方法や解釈、平均点などについて解説します。
コース立方体組み合わせテストとは?

コース立方体組み合わせテストとは、赤,白,青,黄の4色に塗り分けられた立方体のブロックを用いて課題の模様を作る“非言語性”の知能検査になります。
1920年にアメリカの“S.C.Kohs”が発表した知能検査で、日本では1966年に心理学者である“大脇義一”氏が翻案しました。
この検査は積み木を使用することから、“Block Design Test(BD テスト)”と呼ばれることもあります。
特徴
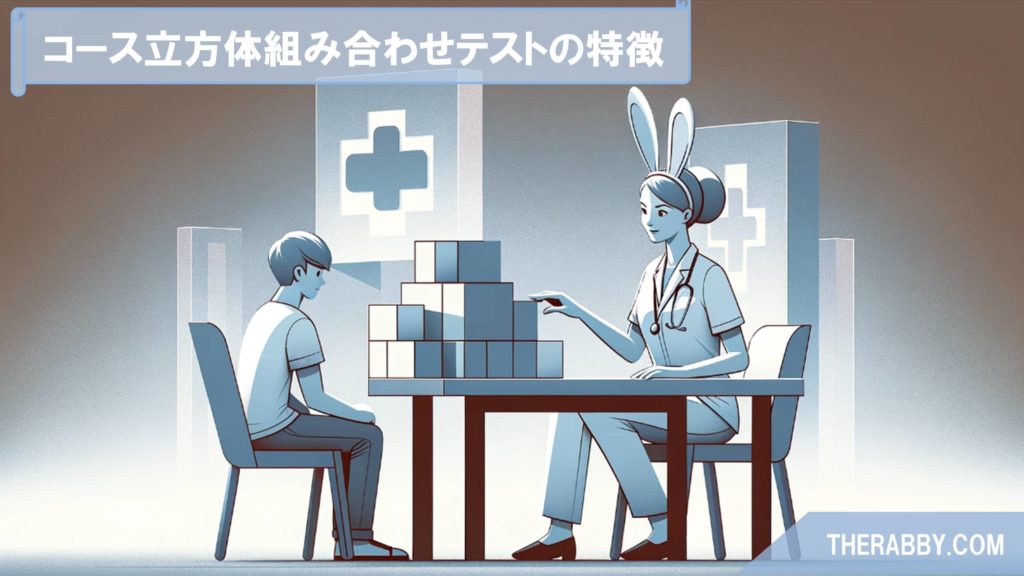
赤,白,青,黄の4色に塗り分けられた立方体を用いて並べるという単純な作業を用いた検査になるため、被験者の手先の器用、不器用は特に影響せずに行うことができます。
また2問連続して課題遂行を失敗した時点で検査が終了になるルールのため、知能の低下が著しい被験者であるほど時間がかからず早く検査終了となるので、負担がかかりにくい…というのも特徴と言えます。
目的について

コース立方体組み合わせテストを実施する目的としては…
- 知能(IQ)の測定
- 構成力の検査
- MCI(軽度認知機能障害)のスクリーニング検査
…があげられます。
対象

コース立方体組み合わせテストの適応対象としては6歳~成人とされています。
検査方法が立方体の積木を使用するという“非言語性”の検査である点からも、聴覚障害や失語症といった言語障害がある場合でも適応とされています。
所要時間

コース立方体組み合わせテストの所要時間は20分から場合によっては50分程度であり、平均35分を要します。


やり方、方法

コース立方体組み合わせテストの実施方法としては、被験者は難易度順に並べられた17問の模様が描かれた課題カードをみて、立方体の積木を課題の模様と同じように並べる…というものになります。
正確に並べるまでの完了時間によって得点が変わっていき、前述したように制限時間内に2連続して課題達成できないとその場で打ち切りになります。
練習問題
本番を始める前に練習課題があります。
この段階で検査方法を理解できず、課題遂行ができない場合はコース立方体組み合わせテスト自体“実施不可”の判断になります。
テスト7
テスト7の段階で形成する形の角度が変わります。
使用する立方体の個数は4つとテスト1~テスト3と変わらないのですが、知的機能の低下や空間認知の低下によってはこのテスト4でつまづく場合が多いように感じます。
テスト10
テスト10の段階で使用する立方体の数が4個から9個に増加します。
この段階で課題遂行につまづく場合もあるので注意が必要です。
テスト12
テスト12で使用する立方体の数が16個に増加します。
構成する図もより複雑になるので検者は被験者の精神的疲労の状態も確認しながら検査を進めていく必要があります。
注意点
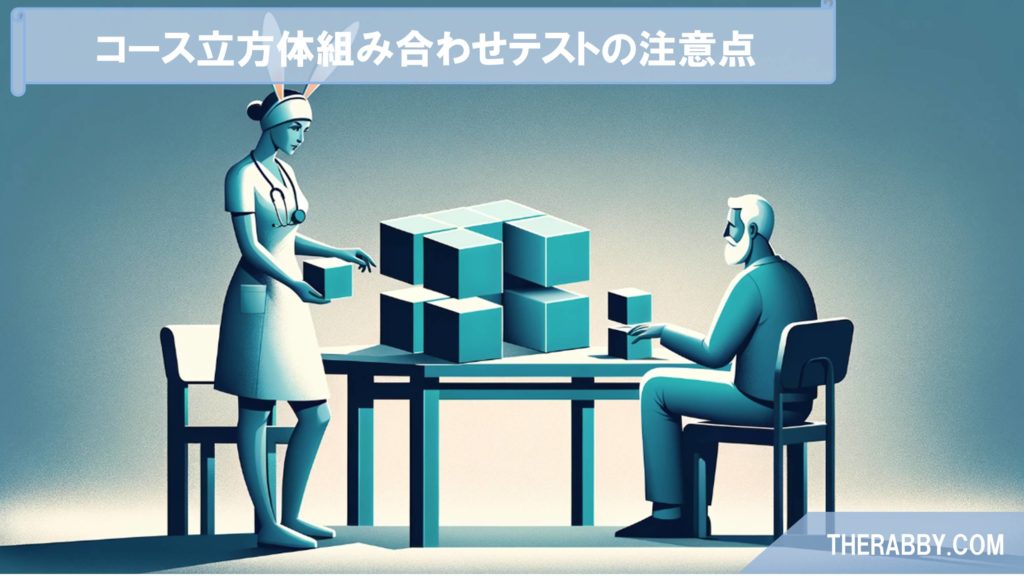
コース立方体組み合わせテストの注意点としては、
- テスト中には色の名前、並べ方を教えることはできない
- 本番前に練習課題があるが、3回繰り返しても理解できない、正解できない場合は検査をうけることができない
- テスト本番中、被験者が間違った並べ方をしたときは「この辺りがおかしいですね」と指摘することはできても、どのように並べたらよいかは教えてはいけない
- 次の課題に進むときは、毎回並べた積木をバラバラにする必要がある
…などがあげられます。
IQの計算方法について

採点は、以下のような流れで行います。
- 得られた総得点から、後述の精神年齢(M.A)換算表により精神年齢を求めます。(例:総得点103点の人は精神年齢16歳1か月)
- 被験者の検査実施日現在で暦年齢(C.A)を求めます。(13才0か月以上は暦年齢修正表によって修正する)
- 『IQ=精神年齢(M.A)/暦年齢(C.A)×100』の公式で知能指数を算出します
コース立方体組み合わせテストのカットオフ値について
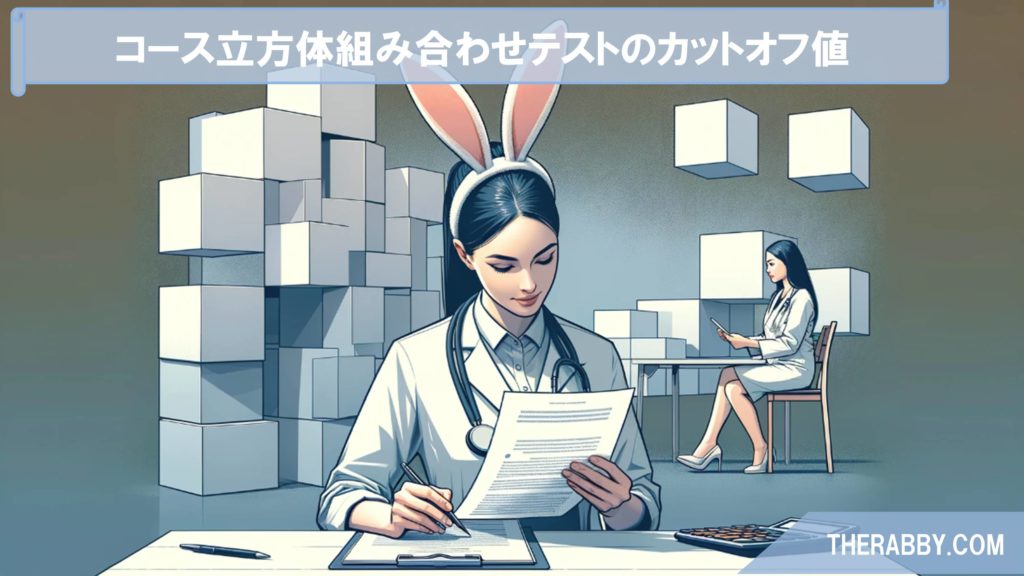
コース立方体組み合わせテストにおいて明確なカットオフ値というものは、IQという知能指数を検査する目的という性質上定められていません。
そのため被験者のIQがその年齢平均に対してどの程度か?という解釈で判断するのが望ましいと考えられます。
コース立方体組み合わせテストと高次脳機能障害
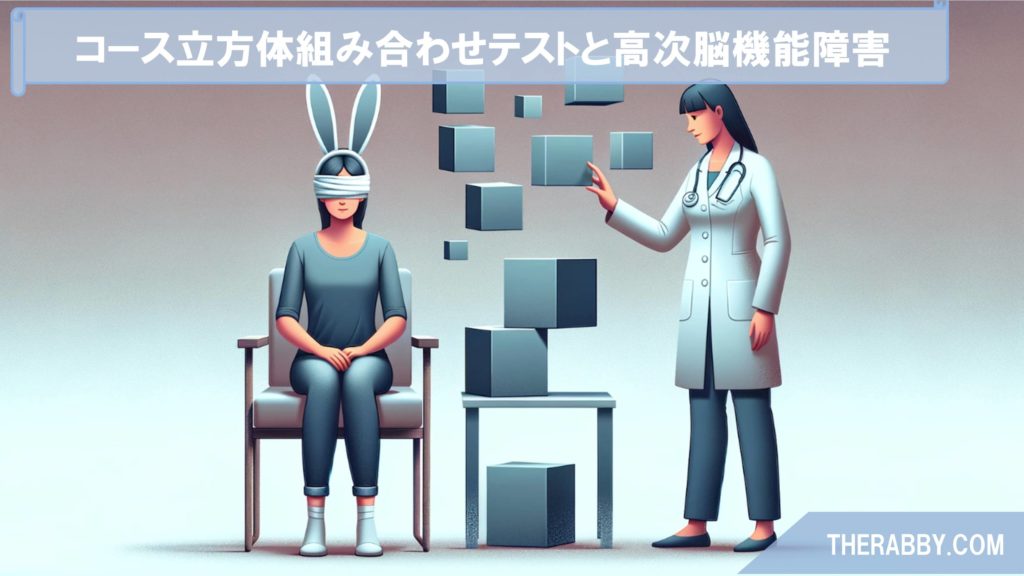
ここでは、主に高次脳機能障害…特に…
- 半側空間無視
- 視空間認知
- 構成失行
…を有する被験者に対してコース立方体組み合わせテストを行う場合のポイントについて解説します。
半側空間無視がある場合
右半球損傷による半側空間無視(USN)では左半分の構成が障害されるのに対して、左半球損傷では左右半分に限らず構成そのものが困難となります。
視空間認知がある場合
視空間失認のクライアントは立方体の色の区別は可能でも、立方体相互間の空間関係の認知が困難な場合があります。
また、心理学者であるA.L.Bentonによる1969年の報告によると、
- コース立方体組み合わせテストは右半球の中心後回障害についての感度が高いこと
M.D.Lezakによる1976年の報告では、
- 知能程度が高いクライアントにおける軽微な視覚構成障害を明確化するのに有用である
との報告もあります。
構成失行がある場合
脳血管障害の被験者で、構成失行を反映する検査としてはコース立方体組み合わせテストが非常に有用的です。
この場合、コース立方体組み合わせテストで決められている時間制限をなくして提示されたモデル通りに構成させ、時間の経過とともに展開し、立方体が構成されてゆく型(各ブロックの位置を構成の順序)を順次検者が紙に画き記録する方法がのぞましいようです。
コース立方体組み合わせテストの診療報酬や保険点数について

コース立方体組み合わせテストは保険診療が可能な検査の一つとして認定されています。
診療報酬の点数としては“80点”ですので、対象者はHDS-Rの検査を受けた際は3割負担の場合は240円、高齢者の場合は1割の場合で80円、2割の場合でも160円の支払いが発生します。
まとめ
今回はコース立方体検査について解説しました。
非言語性の知能検査として有用なコース立方体組み合わせテストですが、その対象年齢も対象範囲も広い作業療法における臨床や現場では非常に使いやすい検査と言えます。
もちろんこのコース立方体組み合わせテストのみですべては判断できませんが、知的能力への評価の一つとして使うといいでしょうね!