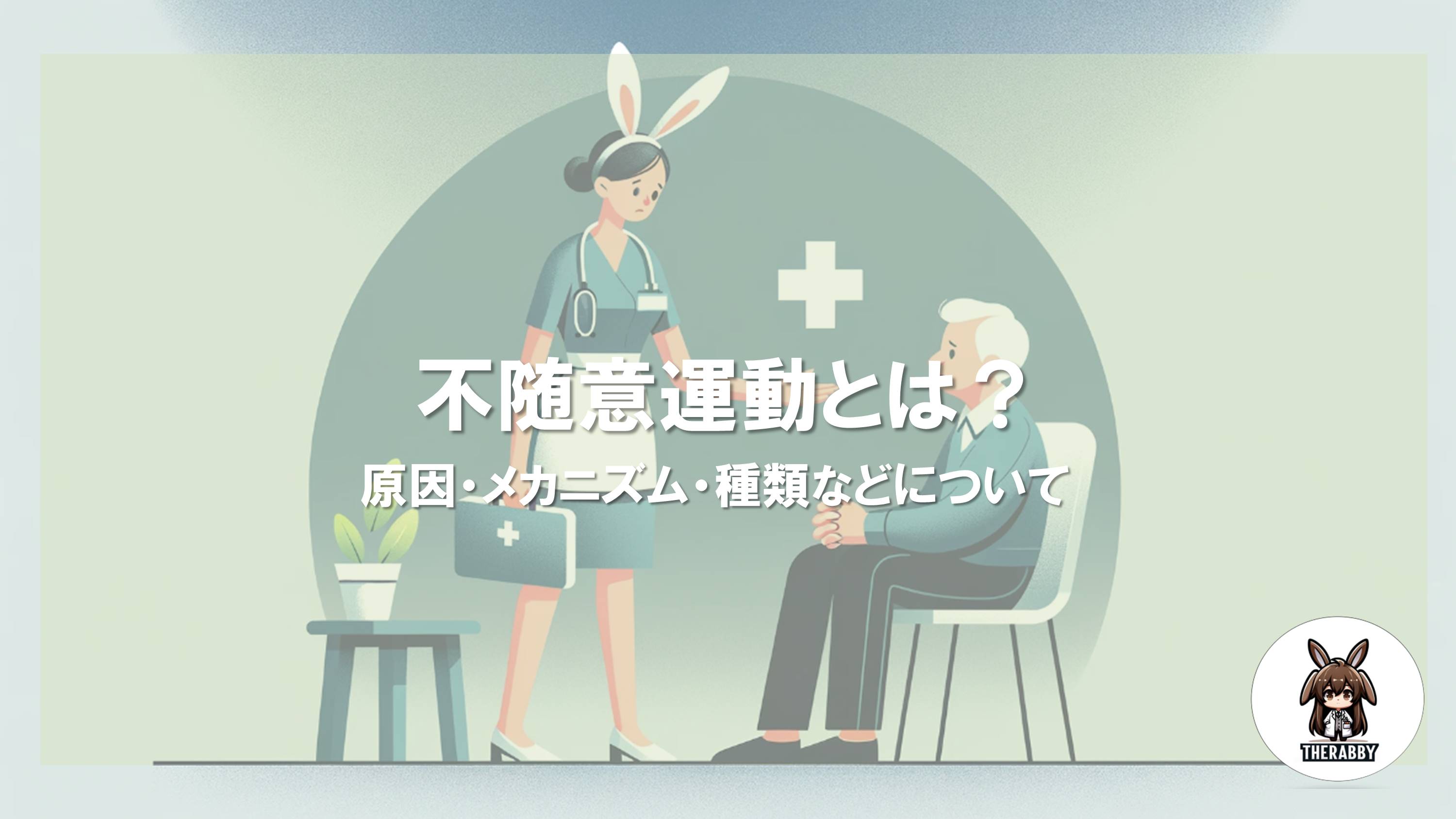パーキンソン病などのリハビリの臨床でみられる症状に”不随運動”があります。
本記事ではこの不随意運動について解説します。
不随意運動とは?

随意運動(Involuntary Movement)は、個体が意識的な制御を行わないで発生する運動のことを指します。
これは、通常、中枢神経系の機能や制御の障害によって引き起こされます。
不随意運動は、個体が自覚的に意図することなく、無意識または自律的に発生します。
わかりやすく一言でいえば、本人の意志に関係なく起こる、無意識の筋肉の動きや体の不規則な動作のことです。
不随意運動の原因疾患について

不随意運動の原因疾患は様々であり、主に…
- 神経変性疾患
- 脳疾患
- 遺伝性疾患
- 代謝異常
- 薬物の副作用
- 脳外傷
- 感染症
- 自己免疫疾患
…といった中枢神経系や筋肉制御に関わる様々な要因によって引き起こされます。
以下にそれぞれ解説します。
神経変性疾患
神経変性疾患は、不随意運動の主要な原因の一つです。
これらの疾患は、神経細胞の異常な変性や死滅によって引き起こされ、運動機能に影響を及ぼします。
例えば、パーキンソン病やハンチントン病などが挙げられます。
パーキンソン病では、ドーパミンを生成する神経細胞の減少が主な要因であり、震えや筋肉の硬直、運動の遅れといった症状が現れます。
ハンチントン病は、遺伝的要因によって引き起こされ、中枢神経系における特定のニューロンの変性が原因で、舞踏病と呼ばれる不随意運動が特徴です。
脳疾患
脳疾患も不随意運動の重要な原因となります。
脳卒中や脳腫瘍、脳血管障害などが含まれ、これらは脳の特定部位に損傷を与えることで運動制御に影響を与えます。
脳卒中の場合、脳内の血流が遮断されることにより、酸素や栄養が不足し、脳細胞が死滅します。
これにより、麻痺や痙攣、震えなどの不随意運動が生じることがあります。
脳腫瘍は、脳組織を圧迫することで神経機能に障害をもたらし、同様の運動症状を引き起こす可能性があります。
遺伝性疾患
遺伝性疾患は、遺伝子の異常によって引き起こされるもので、不随意運動の原因となることがあります。
ハンチントン病やウィルソン病などが代表的な例です。
これらの疾患は、特定の遺伝子変異によって脳の機能に影響を与え、運動制御の障害を引き起こします。
ハンチントン病は、特定の遺伝子の変異により引き起こされ、進行性の運動障害や認知機能の低下を伴います。
ウィルソン病は、銅の代謝異常が原因で、肝臓や脳に銅が蓄積し、運動制御の問題を引き起こします。
代謝異常
代謝異常も不随意運動の原因として重要です。
体内の代謝プロセスに異常が生じると、神経系の機能が影響を受け、運動制御に障害が発生することがあります。
フェニルケトン尿症やウィルソン病などが例として挙げられます。
フェニルケトン尿症は、フェニルアラニンというアミノ酸の代謝が正常に行われないことにより、脳に有害な物質が蓄積し、神経機能に障害をもたらします。
薬物の副作用
薬物の副作用も不随意運動を引き起こすことがあります。
特定の薬物は、神経伝達物質のバランスを乱すことで運動制御に影響を与えます。
例えば、抗精神病薬や抗うつ薬などが不随意運動の原因となることがあります。
抗精神病薬は、ドーパミン受容体をブロックする作用があり、これによりパーキンソン様の運動症状が現れることがあります。
抗うつ薬も、神経伝達物質のバランスを変化させることで、震えや筋肉の痙攣といった不随意運動を引き起こすことがあります。
脳外傷
脳外傷は、不随意運動の原因となることがあります。
交通事故やスポーツによる頭部への強い衝撃などが、脳に損傷を与えることで運動機能に影響を及ぼします。
脳外傷によって脳の特定の部位が損傷を受けると、運動制御の障害が発生し、不随意運動が生じることがあります。
特に、脳の運動野や基底核と呼ばれる領域が損傷を受けると、震えや痙攣、筋肉のこわばりなどの症状が現れます。
脳外傷後のリハビリテーションは重要であり、早期の介入が回復の鍵となります。
感染症
感染症も不随意運動の原因となることがあります。
特定のウイルスや細菌が中枢神経系に感染すると、神経機能に障害を引き起こし、不随意運動が生じることがあります。
例えば、日本脳炎やライム病などが挙げられます。
日本脳炎は、ウイルスが脳に感染し、炎症を引き起こすことで、運動制御の障害をもたらします。
ライム病は、ダニが媒介する細菌感染症であり、神経系に影響を与え、不随意運動を引き起こすことがあります。
感染症の予防と早期治療が重要です。
自己免疫疾患
自己免疫疾患は、不随意運動の原因となることがあります。
自己免疫疾患では、免疫系が自分自身の神経組織を攻撃し、炎症や損傷を引き起こします。
多発性硬化症やギラン・バレー症候群などが代表的な例です。
多発性硬化症は、中枢神経系のミエリン鞘が攻撃されることで、神経伝達が妨げられ、運動制御に障害が生じます。
ギラン・バレー症候群は、末梢神経が攻撃され、筋力低下や運動障害を引き起こします。
自己免疫疾患の管理には、免疫抑制療法が用いられることがあります。


不随意運動の発生メカニズム

そもそも不随意運動はどのような機序で発生するのでしょうか?
結論を言ってしまえば、不随意運動は、運動や姿勢の制御に関与する神経回路や神経伝達物質の異常によって生じることがわかっています。
ここでは…
- 神経伝達物質の異常
- 神経回路の以上
- 遺伝子の異常
- 代謝異常
…について解説します。
神経伝達物質の異常
神経伝達物質の異常は、不随意運動の主要な原因の一つです。
神経伝達物質は、神経細胞間の情報伝達を担う化学物質であり、そのバランスが崩れると運動制御に影響を与えます。
例えば、パーキンソン病では、ドーパミンという神経伝達物質の減少が運動障害を引き起こします。
ドーパミンは運動の調整に関与しており、その不足は震えや筋肉の硬直、動作の遅れをもたらします。
また、グルタミン酸やGABA(γ-アミノ酪酸)などの他の神経伝達物質のバランスも重要であり、これらの異常は多様な不随意運動を引き起こします。
神経回路の異常
神経回路の異常も不随意運動の原因となります。
脳内の運動制御に関与する神経回路は、基底核、視床、小脳、皮質など複数の部位が相互に連携して機能しています。
これらの回路のいずれかに異常が生じると、運動制御に問題が発生します。
例えば、ハンチントン病では、基底核の一部である線条体の神経細胞が変性し、これにより不随意運動が生じます。
さらに、脳卒中や脳外傷によってこれらの神経回路が損傷されると、運動の調整が乱れ、不随意運動が引き起こされることがあります。
遺伝子の異常
遺伝子の異常は、不随意運動の原因となることがあります。
特定の遺伝子変異が神経細胞の機能や発達に影響を与え、運動制御に問題を生じさせます。
ハンチントン病はその代表的な例であり、HTT遺伝子の変異によって引き起こされます。
この遺伝子変異により、異常なハンチンチンタンパク質が生成され、神経細胞の機能を妨げます。
また、他の遺伝性疾患でも、特定の遺伝子変異が神経系の機能に影響を与え、不随意運動を引き起こします。
遺伝子の異常は、家族歴や遺伝子検査によって診断されることが多いです。
代謝異常
代謝異常も不随意運動の原因として重要です。
体内の代謝プロセスに異常が生じると、神経系の機能に影響を与え、運動制御に障害が発生することがあります。
ウィルソン病やフェニルケトン尿症などが例として挙げられます。
ウィルソン病は、銅の代謝異常が原因で、肝臓や脳に銅が蓄積し、神経機能に障害をもたらします。
フェニルケトン尿症は、フェニルアラニンというアミノ酸の代謝が正常に行われないことにより、脳に有害な物質が蓄積し、不随意運動を引き起こします。
代謝異常は、血液検査や遺伝子検査によって診断されることが多いです。


不随意運動の種類

この不随意運動にはさまざまな種類があります。
主なものとして…
- 舞踏運動
- 振戦
- バリスム
- アテトーゼ
- ジストニー
- ジスキネジア
- ミオクローヌス
- チック
…などがあげられます。
それぞれ解説します。
舞踏運動
舞踏運動は、不規則で急速な、不随意の運動が四肢や顔面に現れる運動障害です。
これは特にハンチントン病で顕著に見られる症状であり、患者はしばしば意図しない動きを制御できなくなります。
舞踏運動は、基底核の線条体における神経細胞の変性によって引き起こされます。
この障害は、日常生活に大きな支障をきたし、食事や歩行などの基本的な活動が困難になることがあります。
治療には、ドーパミン受容体拮抗薬や他の運動制御を助ける薬物が使用されることがありますが、根本的な治療法はまだ確立されていません。
振戦
振戦は、規則的なリズムを持つ不随意運動で、通常は手や腕に現れます。
パーキンソン病において一般的に見られるが、本態性振戦など他の原因でも発生します。
この運動は、筋肉の収縮と弛緩の周期的な繰り返しによって引き起こされ、意図的に動作を行う際に悪化することがあります。
振戦は、生活の質を著しく低下させることがあり、書字や食事などの日常的な活動に影響を与えることがあります。
治療には、βブロッカーや抗てんかん薬などの薬物療法が用いられることがあります。
バリスム
バリスムは、大きくて激しい不随意運動で、通常は一側の四肢に現れます。
バリスムの原因は、反対側の大脳基底核の視床下核に病変が生じることが一般的です。
この症状は、脳卒中や脳外傷によって引き起こされることが多く、そのため突然発症することが多いです。
運動は非常に力強く、持続的であり、患者の安全や生活に重大な影響を及ぼすことがあります。
治療には、ドーパミン受容体拮抗薬や筋肉弛緩薬が使用されることが多いです。
アテトーゼ
アテトーゼは、ゆっくりとした、流れるような不随意運動で、特に手や指、顔に現れます。
この運動は、筋肉の持続的な収縮と弛緩によって引き起こされ、緩やかな蛇行運動のように見えます。
アテトーゼは、脳性麻痺や脳の基底核に損傷がある場合によく見られます。
これにより、動作が不規則で制御しにくくなり、細かい動作やバランスの維持が困難になります。
治療には、薬物療法や物理療法が含まれ、症状の管理が中心となります。
ジストニー
ジストニーは、持続的な筋肉の収縮が特徴で、異常な姿勢やねじれた動作を引き起こします。
この症状は、全身性または局所性に発生することがあり、重症度や影響の範囲はさまざまです。
ジストニーの原因は、神経伝達物質の不均衡や基底核の異常によるもので、遺伝的要因や外傷が関与することもあります。
この運動障害は、痛みや疲労を伴い、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。
治療には、ボツリヌス毒素注射や薬物療法、リハビリテーションが用いられます。
ジスキネジア
ジスキネジアは、異常な不随意運動であり、特に顔や四肢に発生します。
パーキンソン病の治療に使用されるレボドパなどの薬物の長期使用に伴う副作用としてよく見られます。
ジスキネジアの運動は、不規則でリズミカルではなく、急激に始まり終わることが特徴です。
この症状は、患者の生活の質を低下させ、特に社会的状況での困難を引き起こします。
治療には、薬物の調整や別の薬物の併用が考慮されることがあります。
ミオクローヌス
ミオクローヌスは、急激で短い不随意筋収縮が特徴です。
これらの収縮は、全身のどこにでも現れる可能性がありますが、特に手や顔に多く見られます。
ミオクローヌスは、てんかんや脳卒中、代謝異常などの多くの病状に関連して発生します。
この症状は、突発的で予測不能であり、日常生活における動作を妨げることがあります。
治療には、抗てんかん薬やその他の薬物が使用され、症状の軽減を目指します。
チック
チックは、突然で繰り返し行われる不随意運動や音声の発声です。
一般的に、顔、首、肩などの筋肉に現れ、トゥレット症候群の一部としても知られています。
チックは、ストレスや疲労により悪化することが多く、患者自身が一時的に抑制することは可能ですが、完全に制御することは困難です。
症状は通常、子供の頃に始まり、成長とともに軽減することがありますが、一部の人では成人期まで続くことがあります。
治療には、行動療法や薬物療法が使用されることがあります。