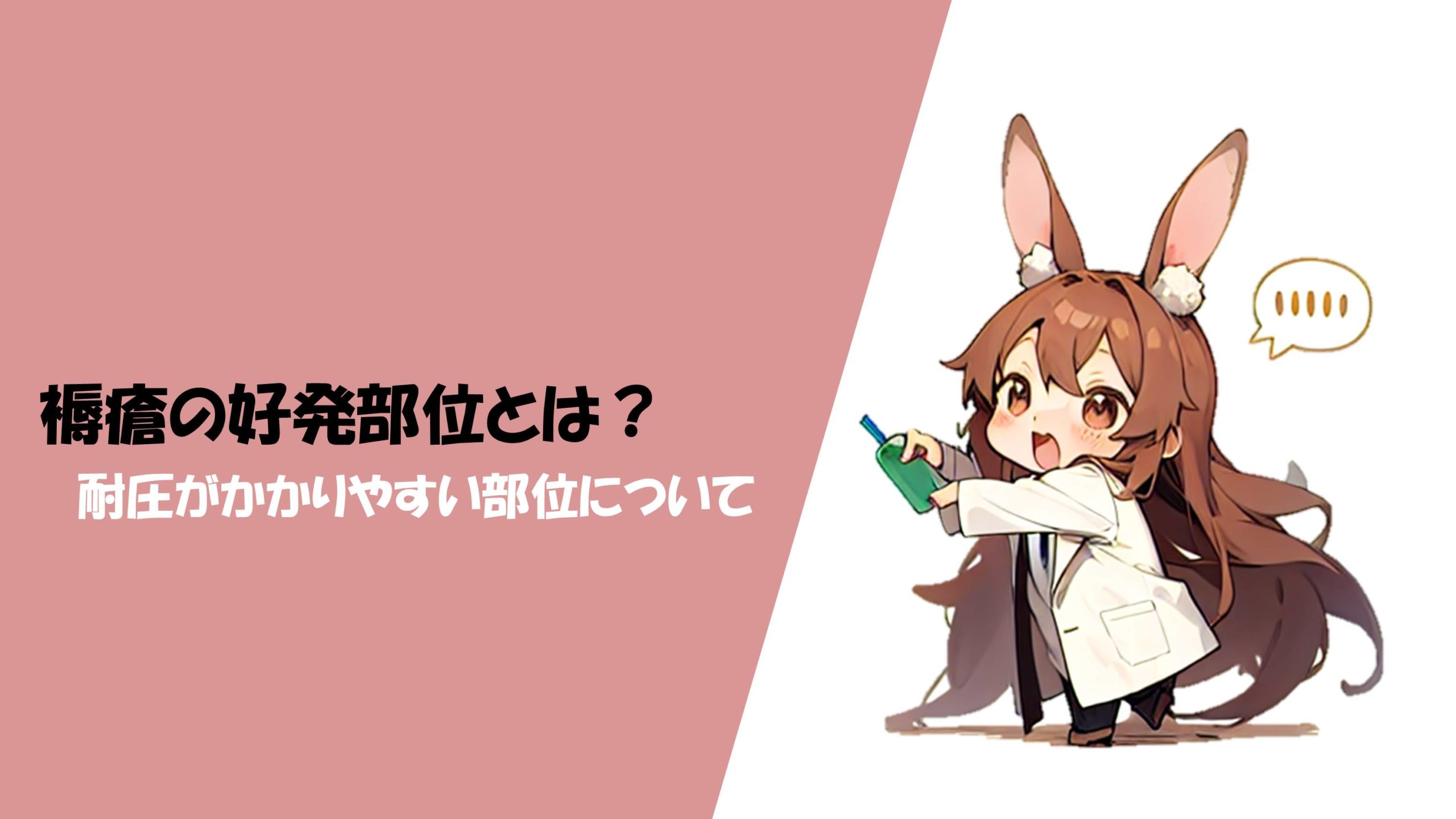褥瘡は、長期の臥床や座位により特定の体部に圧力が集中することで発生します。
本記事では褥瘡の好発部位について解説します。
褥瘡の好発部位
上述したように、褥瘡は骨が隆起している部位(骨突出部)にできやすいとされています。
基本的に耐圧がかかりやすい部位としては…
- 仙骨部
- 背部
- 腸骨部
- 大転子部
- 下腿部
- 踵部
- 頭部
- 肩部
- 耳部
…などがあげられます。
それぞれ解説します。
仙骨部
仙骨部は、特に臥床している患者において褥瘡が発生しやすい部位です。
この部分は体重が集中しやすく、長時間の臥床により圧力が持続するため褥瘡のリスクが高まります。
特に、硬いベッドや不適切なマットレスを使用している場合、圧力が更に集中し褥瘡が生じやすくなります。
背部
背部は、長時間の座位や臥床によって圧力がかかりやすい部位です。
特に脊椎の周辺や肩甲骨下部に褥瘡が発生しやすいことが知られています。
背部の褥瘡は、硬い背もたれや椅子、ベッドの使用によっても引き起こされることがあります。
腸骨部
腸骨部は、体を横にした際に圧力が集中する部位で、特に側臥位をとる患者において褥瘡のリスクが高まります。
この部位は骨突出があるため、皮膚への圧力が高くなりやすく、適切な体位変更やクッションの使用が重要です。
大転子部
大転子部は、股関節の外側に位置し、特に側臥位で長時間過ごす患者において褥瘡が生じやすい部位です。
この部位は骨が皮膚に近く、圧力によって皮膚の損傷が起きやすいです。
適切な支持体やクッションの使用が予防に効果的です。
下腿部
下腿部は、特に車椅子を使用する患者や臥床状態の患者において、褥瘡のリスクが高い部位です。
圧力が長時間にわたり加わることで、特に膝の裏や腓骨頭周辺に褥瘡が生じやすいです。
下腿部の褥瘡は、適切な体位変更やクッションの使用で予防することが可能です。
踵部
踵部は、長時間の臥床により特に褥瘡が生じやすい部位です。
この部位は骨と皮膚の間の組織が少ないため、圧力による影響を受けやすく、褥瘡のリスクが高まります。
適切な足元のサポートや体位変更が予防策として重要です。
頭部
頭部は、特に人工呼吸器を使用している患者や長時間の臥床を余儀なくされている患者において褥瘡が生じやすい部位です。
頭部の圧力が持続すると、特に耳の後ろや頭蓋骨の突出部に褥瘡が発生しやすくなります。
頭部の褥瘡予防には、頭部の適切な支持や定期的な体位変更が効果的です。
肩部
肩部は、長時間の座位や臥床によって圧力がかかりやすい部位です。
特に肩甲骨の周辺は圧力に敏感で、褥瘡が生じやすいことが知られています。
肩部の褥瘡予防には、定期的な体位変更や適切なクッションの使用が重要です。
耳部
耳部は、特に長時間の臥床状態や硬い枕の使用により、褥瘡が生じやすい部位です。
耳の後ろや耳の下は圧力が集中しやすく、これが褥瘡の原因となります。
耳部の褥瘡予防には、柔らかい枕の使用や定期的な体位変更が効果的です。