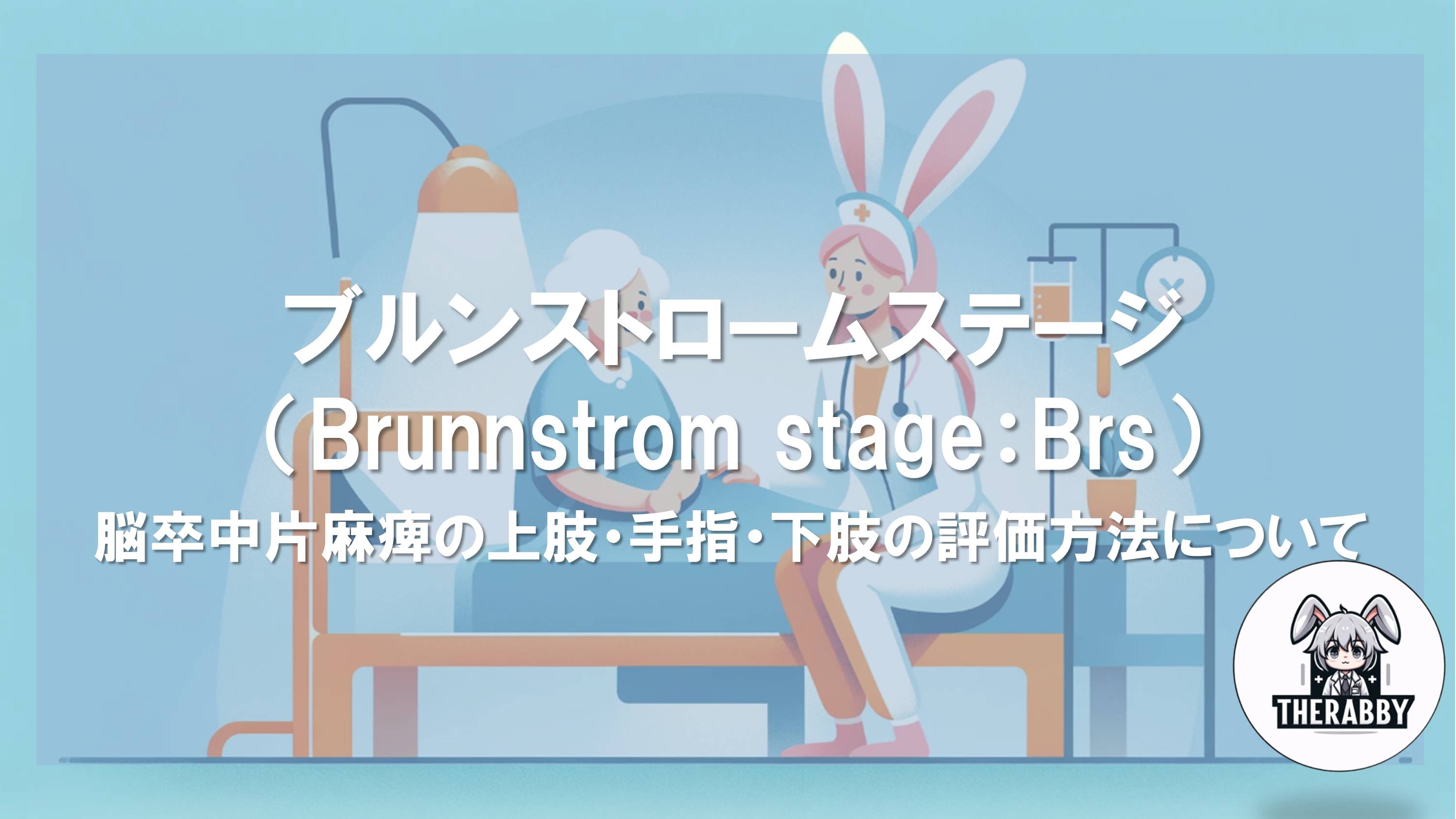脳卒中片麻痺の評価方法として最も多く使われているであろうブルンストロームステージ(Brunnstrom stage:Brs)。
今回はこのブルンストロームステージの評価方法や目的、上肢、手指、下肢それぞれの評価ポイントについて解説します。
ブルンストロームステージ(Brunnstrom stage)とは?
ブルンストロームステージ(Brunnstrom stage:Brs)は、スウェーデンのシグネ・ブルンストローム(Signe Brunnstrom)により考案された脳血管障害による片麻痺の評価・検査法です。
彼は1950~1960年代の臨床観察を通し、片麻痺の回復過程に一定の法則があつことを発見しました。
その発見から、脳卒中発症初期からの一貫したリハビリテーションプログラムを多症例経験した中から生み出した理論体系がこのブルンストロームステージになります。
臨床では“BRS”といった略称で使用される場合が多いと思います。
概要
ブルンストロームステージは脳卒中の運動麻痺の回復過程を順序により判断するために考案されました。
そして回復が進むにつれて共同運動から分離した動作へと移行し、徐々に正常な動作へ近づいていくという一連の回復過程を1~6の6段階で検査、評価します。
尺度としては“順序尺度”として用いられています。
ブルンストロームステージの目的について
そもそもこのブルンストロームステージを用いて評価する目的、意義はなんでしょうか?
当たり前でしょうけど端的に言えば、「クライアントはどの程度上肢、下肢、手指を自由に動かせるのか?を調べるため」となります。
つまり、脳卒中片麻痺であるクライアントの筋力の有無を評価するのではなく、その段階での「筋出力の質」を評価することになります。
加えて、“連合運動”や“共同運動”からの分離の度合を測定しすることで、今後どの程度の回復過程を辿っていくか(大まかにですが)予後予測を立てることができます。
ブルンストロームステージの回復ステージ
基本的には上肢、手指、下肢といった四肢に関係なく次のような回復ステージを辿ることになります。
- Stage Ⅰ(ステージ1)
- Stage Ⅱ(ステージ2)
- Stage Ⅲ(ステージ3)
- Stage Ⅳ(ステージ4)
- Stage Ⅴ(ステージ5)
Stage Ⅰ(ステージ1)
弛緩性麻痺(完全麻痺)で、筋肉がダラッと緩んでしまっている状態。
完全に弛緩していて、自分では全く動かせません。
随意運動も腱反射の反応もみられません。
脳卒中発症早期によく見られる状態です。
Stage Ⅱ(ステージ2)
連合反応が出現する段階になります。
つまり随意的ではない筋収縮や運動がみられる状態です。
腱反射の出現や、非麻痺側の一部を強く動かすことで筋収縮が起こる“連合反応”がみられます。
あくびやくしゃみをして瞬間的に動く現象もこのステージでみられ始めます。
Stage Ⅲ(ステージ3)
基本的な“共同運動”のパターンが起こりはじめる状態です。
それぞれの筋肉のみを随意的に動かそうとしても、他の付随する筋肉までいっしょに動いてしまい分離した運動が困難な状態といえます。
この共同運動には“屈筋共同運動”と“伸筋共同運動”の2種類のパターンがあります。
Stage Ⅳ(ステージ4)
分離運動が出現する段階であり。随意的に動かそうとしても全体の一塊で動いてしまう共同運動から脱する段階です。
それぞれの関節が随意的に分離して動くようになります。
Stage Ⅴ(ステージ5)
分離運動が進行してくる段階です。
共同運動・痙性の出現が減弱し、より多くの分離運動が可能になります。
Stage Ⅵ(ステージ6)
さらに分離が進み正常に近づいてくる段階で、共同運動・痙性の影響がほとんどなくなってきます。
関節運動もスピーディーに可能で、より協調的にそれぞれの関節が自由に随意的に動かせます。
しかし、必ずしも「正常」ではなく、どこかぎこちなさが残ることが多くあります。
上肢のブルンストロームステージ
| Stage | 運動の状態 |
|---|---|
| Stage.Ⅰ | 随意運動なし(弛緩状態) |
| Stage.Ⅱ | 基本的共同運動、またはその要素が連合反応や随意運動として出現する。 |
| Stage.Ⅲ | 基本的共同運動またはその要素を随意的に行われる。痙性は強くなり、最大となる |
| Stage.Ⅳ | 痙性は減少し始め、基本的共同運動から逸脱したいくつかの運動の組み合わせが可能になる。 |
| ①.手を腰の後ろにもっていく | |
| ②.上肢を前方水平位に拳上できる | |
| ③.肘90°屈曲位で前腕の回内・回外ができる | |
| Stage.Ⅴ | 基本的共同運動から比較的独立した運動がほとんど可能になる。痙性はさらに減少する。 |
| ①.上肢を横水平位まで上げられる(肘伸展,前腕回内位) | |
| ②.上肢を屈曲して頭上まで上げられる(肘伸展位) | |
| ③.肘伸展位での前腕の回内・回外ができる | |
| Stage.Ⅵ | 分離運動が自由に可能である。協調運動がほとんど正常にできる。痙縮はほとんど認められない |
手指のブルンストロームステージ
| Stage | 運動の状態 |
|---|---|
| Stage.Ⅰ | 弛緩麻痺 |
| Stage.Ⅱ | 指屈曲が随意的にわずかに可能か、またはほとんど不可能な状態 |
| Stage.Ⅲ | 指の集団屈曲が可能、鉤型握りが可能も離すことはできない。 |
| 指伸展は随意的には困難だが、反射による伸展は可能なこともある | |
| Stage.Ⅳ | 横つまみが可能で、母指の動きにより離すことも可能。 |
| 指伸展はなかば随意的にわずかに可能 | |
| Stage.Ⅴ | 対向つまみができる。円筒握り、球握りなどが可能。 |
| 指の集団伸展が可能だが、その範囲は一定していない | |
| Stage.Ⅵ | すべての種類のつまみ方が可能になり、上手にできる。 |
| 随意的な指伸展が全可動域にわたって可能。指の分離運動も可能である。しかし健側より多少拙劣さがみられる |
下肢のブルンストロームステージ
| Stage | 運動の状態 |
|---|---|
| Stage.Ⅰ | 弛緩麻痺 |
| Stage.Ⅱ | 下肢の随意運動がわずかに可能か、またはほとんど不可能な状態 |
| Stage.Ⅲ | 座位や立位で股・膝・足関節の屈曲が可能になる。 |
| Stage.Ⅳ | 座位で足を床上に滑らせながら、膝屈曲90°以上可能になる。 |
| 座位でかかとを床につけたまま、足関節の背屈が可能 | |
| Stage.Ⅴ | 立位で股関節を伸展したまま、膝関節の屈曲が可能になる。 |
| 立位でマヒ側足部を少し前方に出し、膝関節を伸展したまま、足関節の背屈が可能になる。 | |
| Stage.Ⅵ | 立位で股関節の外転が、骨盤挙上による外転角度以上に可能。 |
| 座位で内側・外側のハムストンリングスの交互収縮により、下腿の内旋・外旋が可能(足関節の内返し・外返しを伴う) |
ブルンストロームステージのエビデンスグレードについて
脳卒中片麻痺へのリハビリテーションの臨床、現場で非常に多く使用されているブルンストロームステージですが、じつはエビデンスのグレードとしては「信頼性、妥当性が一部あるもの」とされる“推奨グレードB“になります。
ちなみにステージBについては、
Brunnstrom stage 自体の妥当性・信頼性を検定した研究が極めて少ない。
また, Fugl-Meyer assessment や Chedoke-McMaster strokeassessment の項目に Brunnstrom stage の基準が使われているために,Brunnstrom stage自体の使用頻度は少なくなるが,コンセプト自体は残る評価法である
引用:推奨グレードの決定およびエビデンスレベルの分類(日本理学療法士協会)
…ともあることから、もしかすると今後ブルンストロームステージよりもグレードの高いエビデンスの評価方法が開発されるかもしれませんね。
日常生活活動(ADL)とブルンストロームステージ
ADL動作を考える際、ブルンストロームステージがⅠ~Ⅱの場合は動作に伴う痛み…特に亜脱臼の誘発、増悪に注意が必要です。
ステージⅢ以上の場合は逆に過活動による麻痺側の痙性亢進からくる拘縮や痛みに注意を向ける必要があります。
必要以上の動作を行い、痛みを誘発しないためにもADL能力の評価はしっかりと行っておかなければなりません。
APDL・IADLとブルンストロームステージ
APDL・IADLを考える際にですが、決してブルンストロームステージが低いからといってAPDL・IADL動作が不可能…というわけではないということを念頭において介入をしないといけません。
というのも、ステージがⅠやⅡだから、片麻痺の障害としては”重度=APDL・IADLは不可能”と早合点しがちな若いセラピストが多いような気がするからです(苦笑)。
たしかにステージⅠ、Ⅱの段階だと多くのAPDL・IADL動作は困難にはなるでしょうけど、決して不可能ではないんです。
クライアント自身の機能回復が困難な場合こそ、福祉用具や環境調整といった代替アプローチをとることで、本人が望む活動や参加を実現化していく…という発想が必要です。
そのためにこそAPDL・IADLとICFの関係性についてしっかりと頭に叩き込んだうえで、クライアントの障害像を解釈していく必要があるといえます!
就労支援とブルンストロームステージ
脳卒中片麻痺の方の就労支援に関わる際、注意することとしては「活動量とステージ」になります。
ブルンストロームステージがⅢ~Ⅳの場合は特に、職業生活による過活動によって痙性の亢進、関節拘縮の進行、痛みの発生や増悪、動作効率の破たんへと発展し、職業生活の大きな阻害因子になる場合が多くあります。
クライアントにとって職業生活はADL、APDL(IADL)の動作、活動範囲、負荷量よりも大きくなることは確実です。
そのためブルンストロームの回復ステージの過程と注意点についてはクライアントにもしっかり理解できるよう説明しておく必要がありますね!
ブルンストロームステージと予後予測について
ブルンストロームステージからそのクライアントの上肢・下肢・手指の機能がどの程度まで回復するかの予後予測を立てることが可能です。
- 上肢・下肢ともに発症後2週以内にstageⅣ以上なら、年齢に関係なく6ヶ月以内にほとんどがstageⅥまで回復する
- 発症1ヶ月経過した段階でstageⅣの場合はstageⅥまで回復する患者は2割
- 発症1ヶ月経過した段階でstageⅤまで回復していれば9割はstageⅥに回復する
- 発症時stageⅢの場合はstageⅥまで回復するのは半数
- 下肢の麻痺は発症後2週で47%、1ヶ月で72%、2ヶ月で86%、3ヶ月で94%の回復に達する(発症3ヶ月以降の回復はほとんど期待できない)
- 完全麻痺の場合、年齢による影響が大きく、70歳以上ではほぼ半数が永遠に完全麻痺
*研究内容によって違いはありますし、その個人差もありますから一概には言えませんのでご了承ください。